とにかくプロジェクトの品質とコスト、納期(QCD)を守ることを最優先に——。長年勤めた全日本空輸(以下、ANA)を退職し、LCCのピーチ・アビエーション(以下、ピーチ)での事業立ち上げを経験した後、再びANAに戻った野村泰一氏(業務プロセス改革室 イノベーション推進部 部長 兼 ANAHD デジタルデザインラボ エバンジェリスト)が目にしたのは、標準化とQCDの死守に固執しすぎて、身動きが取れなくなった古巣IT部門の姿でした。
皆、真面目に懸命に働いているのに、先のことを考える余裕がないほど常に膨大な量の仕事に追われ、そもそも「何のための仕事なのか」を見失っている——。そんな状況を前にした野村氏は、自身がピーチ・アビエーションで経験したSaaS的、アジャイル的な考え方と取り組みをANAのIT部門に浸透させることで事態を改善し、イノベーティブな組織に変えられるのではないかと考えるようになりました。
部門ごとのサイロ化をなくして風通しを良くし、関係する部門が力を合わせて課題の解決に向き合う。仕組みやサービスは「作って終わり」ではなく、そこをスタート地点に、みんなで「最初は見えなかった要件」を発見し、“作りながら使いながら”育てていく。そして何より、メンバーが目的意識を持ち、ワクワクした気持ちでANAの未来を創造できる場を作っていこう——。
そう決意した野村氏は、どんなアプローチでANAのIT部門を変えていったのでしょうか。歴史ある大企業に変革をもたらすまでの軌跡についてお聞きしました。
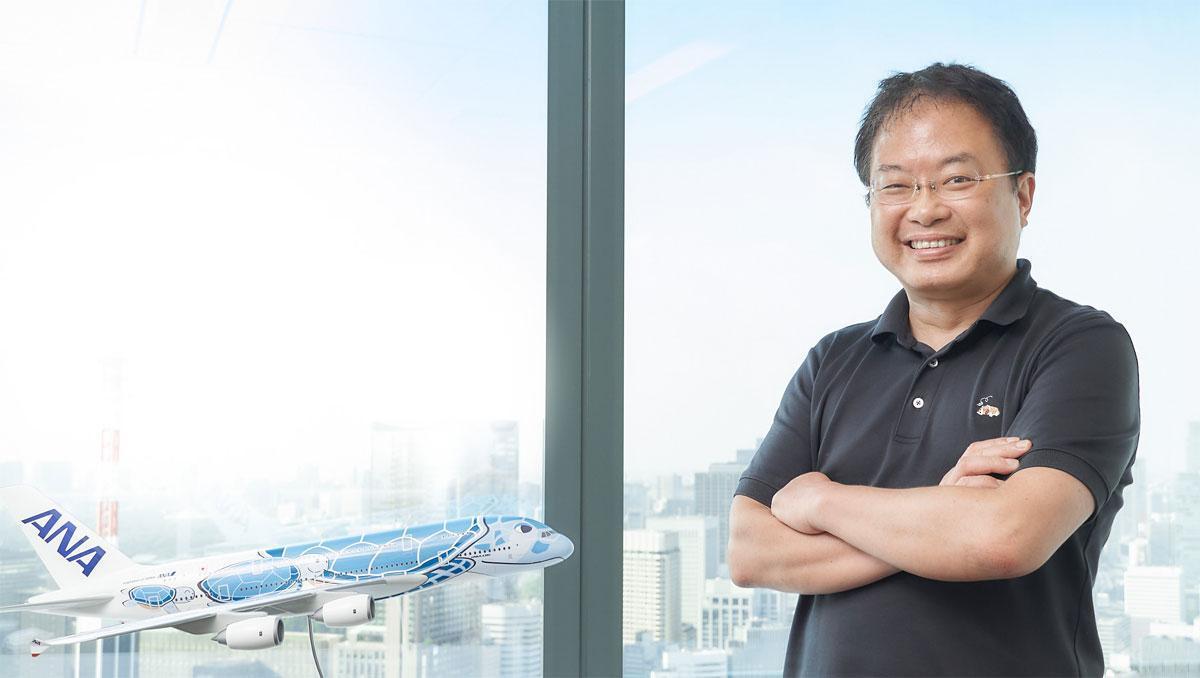
【野村泰一氏プロフィール】インターネット予約やスキップサービスなどANAの予約搭乗モデルをデザイン。日本初のLCCであるピーチ・アビエーションの創設に携わった後、2017年4月より現職。最近では、ロボット、IoT、AIなどのデジタルテクノロジーを活用する一方で、働き方改革の推進にも関わっている。
仕事の本質を見失わせ、組織の停滞を生む「行き過ぎた標準化」の弊害とは
── ANAのIT部門は野村さんにとっていわば古巣ですが、ピーチ・アビエーションから戻ったときの印象はいかがでしたか?
野村泰一:一言で言えば、「一生懸命、真面目に頑張っている」という印象でした。ただし、クリエイティブな仕事をしている印象や、会社全体のビジネスに積極的にコミットしている印象は残念ながら受けませんでした。とにかく決められた手順を真面目に守りながら、ひたすら案件ごとのQCD(Quality・Cost・Delivery)を守る。何か新たな価値を生み出せるようなプロセスや余裕がなかったのです。
ANAがこのような状況に陥った背景は、航空事業が人の命を預かるビジネスであり、社会的責任が大きいことにあると思います。公共性の高い事業では確実性が求められるので、システム作りにおいても“失敗してはいけない”という気持ちを強くしすぎてしまったのかもしれない。ただ、正直なところ、「このままではこの組織は社内で“不要論”が出てしまうのではないか?」と危惧していました。
── 停滞の原因は、どこにあったのでしょうか。
野村泰一:私がかつて所属していた頃と比べ、「標準化」がかなり進んでいました。標準化そのものは決して悪いことではありませんし、業務やサービスの品質を担保するためには重要な取り組みであることには間違いありません。
しかし、標準化が行き過ぎてしまうと、細かな標準や手順を守ることだけに意識が向いてしまうあまり、「そもそも、このプロジェクトで自分たちは何を目指しているのか?」「この仕事で、誰のためにどのような価値を生み出そうとしているのか?」といった本質や大局に目が向かなくなってしまいます。
結果として、個々の案件のプロジェクト管理を形式通りにこなすことだけに終始することになり、思わず「この仕事をしていて楽しいの?」とメンバーに尋ねてしまったこともありました。
── 標準化の取り組みも、行き過ぎると弊害が出てしまうのですね。
野村泰一:標準化が進んだ組織では、「標準に沿って計画を正確にこなしていくこと」が良しとされ、「そこから逸脱することは悪」だと見なされます。しかし、環境の変化が激しい今の時代においては、当初掲げた方向が変わることは往々にしてあるのです。
そういう場合は、状況の変化に応じて柔軟に方向を変更していくことが望ましいのですが、標準化が行き過ぎた組織はそうした変化に対応できず、状況や環境がどれだけ変わっていても当初のプランの完遂に固執してしまいます。
レガシーなIT組織にアジャイル的・SaaS的な考え方を浸透させる方法とは
── そうした文化を変えるために、どんなことに取り組んだのですか。
野村泰一:まずはメンバーのマインドセットを変える必要があると考え、目指すべきマインドチェンジの方向性を、宮本武蔵が記した兵法書に例えた「五輪書」というドキュメントにまとめました。本物の五輪書と同じく、「風の巻」「水の巻」「火の巻」「土の巻」「空の巻」の5つのパートからなり、それぞれイノベーション実現のための具体的なマインドセットを示しました。

これを単なるお題目としてではなく、人事評価の指針としても定めました。例えば五輪書の中には「65点でも動こう」という項目がありますが、これは単なるスローガンではなく、チームメンバーの業績評価を行う際の基準として採用しています。つまり「80点や90点で堅実な仕事をした人」より、「たとえ失敗したとしても65点で動いた人」の方を私は高く評価する、ということです。
── かなり大胆なマインドチェンジを打ち出したのですね。
野村泰一:「65点で動こう」というのはつまり、「失敗を恐れずにとにかく行動しよう」ということを言っています。歴史ある大企業ほど、どうしてもカルチャーが保守化してしまい、必要以上に「失敗を恐れてチャレンジすること」よりも「計画や標準を守ること」にこだわりがちです。これはシステム開発の方法論でいえば、ウオーターフォール型と相性がいいやり方ですね。
確実性が求められる航空業界では、ウオーターフォール型のアプローチも必要ですが、それだけではなく、案件によってはとにかく素早く行動に移して、「走りながら考える」アジャイル的なアプローチ、その都度必要なものを素早く取り入れていくSaaS的なアプローチも推奨して、それまで「標準化」でがんじがらめになっていた組織に、「むしろ標準から逸脱した“例外”をどんどん作っていこう!」と掛け声をかけていったんです。
── それまで「標準を守ること」を至上命題にしていた人たちにとっては、かなり大きな変化だったでしょうね。
野村泰一:そうですね。また、これと並行して、最新テクノロジーに触れる機会をどんどん増やしていきました。標準化に縛られた組織では、どうしても意識が「内向き」になりがちで、世の中の技術トレンドなどに興味が向かなくなってしまいます。
そこで、標準化の枠組みの外で最新テクノロジーを積極的に試すPoC(Proof of Concept:概念実証)のプロセスを作ったり、これまで付き合いのなかったITベンダーのキーマンと定期的に勉強会を開くなどして、社外でテクノロジーと出会う場を意識的に作っていきました。
さらにこうした考えを推し進め、これまでのように業務側の要請にテクノロジーで応えるだけではなく、テクノロジーを武器にIT部門側から業務側の課題解決の提案ができるような仕事のやり方をメンバーと一緒に模索するようになりました。これを実現するために、テクノロジードリブンのチームを新たに作ったのもこの頃でした。
── 実際にはどのような成果が表れたのでしょうか。
野村泰一:それまでIT部門のメンバーは「IT部門のカバー範囲はここまで、ここから先は管轄外」と、自ら業務範囲に縛りを設けていました。これをいったん取り払い、それまでIT部門が管轄してこなかった業務領域にも積極的に入り込んで、RPAなどのテクノロジーを使って業務課題の解決に自ら取り組むようにしたところ、業務現場からとても感謝してもらえるようになったんですね。
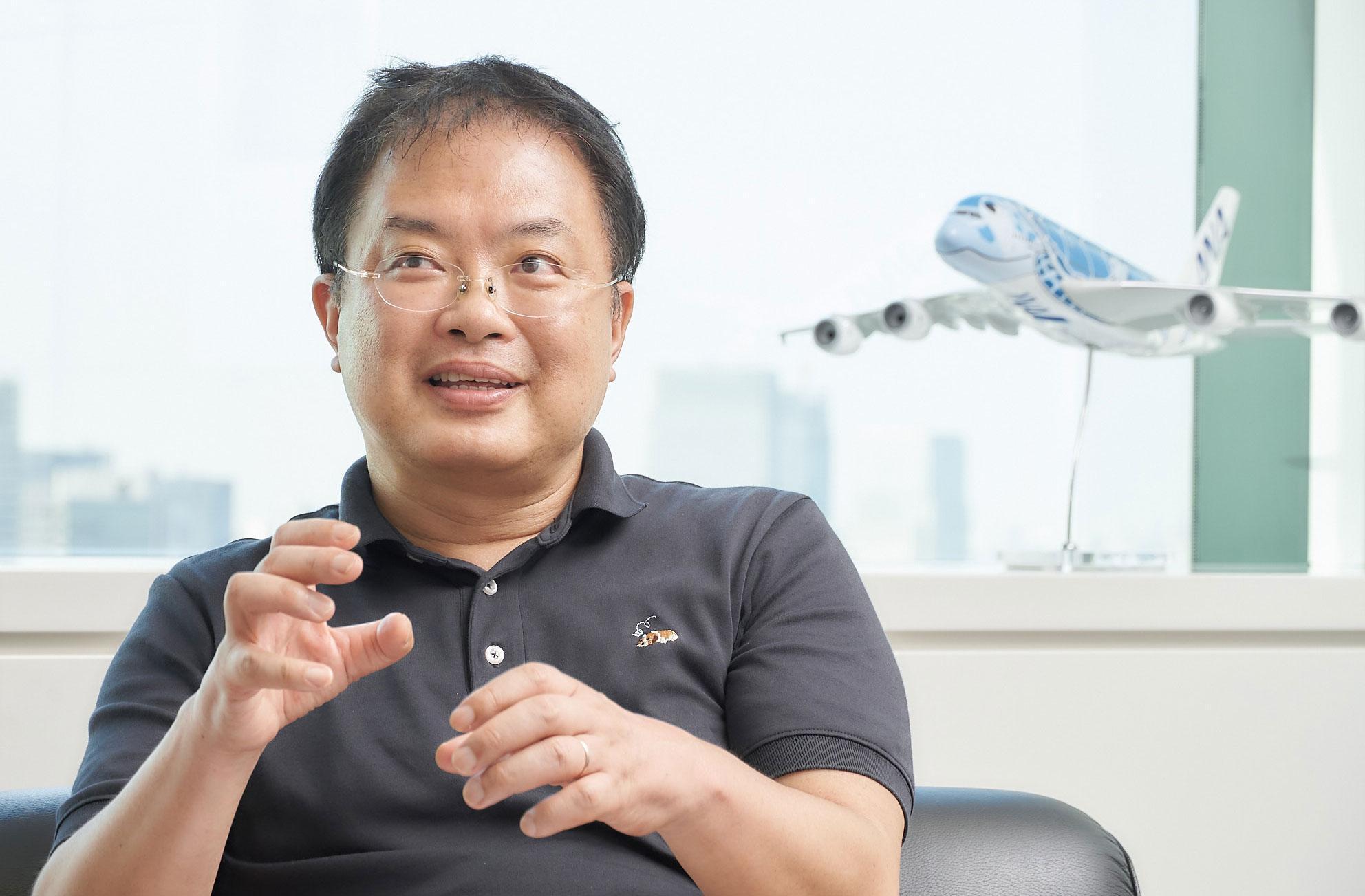
こうした成果で手応えをつかんだので、IT部門が扱っているテクノロジーと業務部門が抱えている業務課題とのマッチングを行うワークショップを社内で定期的に開催するようになりました。この場を通じて実際に業務課題の解決へとつながった例も多く、メンバーのマインドが変わってきたのを肌で感じたのもこの頃でしたね。自ら考えて働くようになり、皆の表情が明るくなってきたのはうれしい変化でした。
データ活用プロジェクトを通じて「異なる部門」に横串、新たな価値の創出へ
── SaaS的、アジャイル的なアプローチはマインド面だけでなく、実際のシステム構築にも取り入れていますが、その効果は?
野村泰一:これは私自身のピーチでの経験が大きく影響しています。ピーチではANAのようなメインフレームの大規模なシステムではなく、SaaSアプリケーションを組み合わせることで、早く低コストでシステムを構築する手法をとりました。
しかし、これだけでは他社との差別化が図れないため、APIを通じてさまざまなデータをかき集め、それらを活用することで自社独自の強みを出していました。この経験から、ANAに戻った後も会社の活力を生むには「データ活用」が鍵を握るとずっと思っていました。
しかし当時のANAは、各部署のシステムごとにデータが囲い込まれており、互いのデータを組み合わせて新たな価値を生むための土壌がありませんでした。そこで、あらゆるシステムを横断する共通のデータ基盤(データレイク)を新たに設け、APIを通じて各基幹システムからデータを収集して一元管理できる仕組みを構築しました。
これらのデータは、同じくAPIを通じて外部アプリケーションから自由に利用できるようになっていますから、これまでは不可能だったデータの組み合せが可能になり、部署を横断した課題解決につながるPoC(実証実験)が次々と立ち上がっています。
── 自由なデータの組み合わせで実現した実証実験には、どのようなものがありますか。
野村泰一:例えば、特定便のお客様に対して、搭乗日の前日に「45分前までに保安検査場を通ったら、中の売店で使える500円クーポンを進呈」という案内を送ったところ、それまでは30分前にピークが来ていた保安検査が45分前に前倒しになるとともに、売店の売り上げも上がるという結果が得られました。
この仕組みは、先ほどの共通データ基盤をベースにチェックインのシステムや店舗系システムを連携させた例ですが、これまではばらばらだった空港オペレーションと売店事業をデータを介してつなげることで、複数の部門の課題解決への道を開くとともに、空港ビジネスに全く新しい価値を生み出すことに成功しました。
── 部門横断のデータ活用プロジェクトを通じて組織に横串を刺すことで、これまでになかった新たな事業やサービスが生まれる可能性が出てくるわけですね。
野村泰一:そうですね。これまでアプリケーション開発やインフラ運用が主力業務だったIT部門でも、今後はデータに着目することで、より会社全体のビジネスに貢献できるようになると考えています。事実、私たちも、データドリブンのチームを新たに設けており、データ活用による事業への貢献をさらに深めていきたいと考えています。既に多くの成果が上がっていますが、さらに経営に大きなインパクトを残せる結果が出せると思っているので、まだまだこれからが本番ですね。
伝統的な組織を変えていくために不可欠なのは
── 企業のIT部門が変わっていくためには何が重要だとお考えですか?
野村泰一:IT部門が手掛けている活動を、もっと社内に知ってもらうためのプロモーション活動は重要だと感じています。せっかく面白い取り組みをしていても、それが社内で知られていないと活動の幅がなかなか広がっていきませんから、自分たちの活動を外に向けて積極的に発信していく力は必要だと思います。私たちも、社内SNSで自分たちの取り組みについて紹介したり、テクノロジーを手軽に体験してもらうちょっとした社内イベントを企画するなど、社内のプロモーション活動をいろいろ展開しています。
また、経営と密接にコミュニケーションを取ることも大事だと思います。ともすると、経営からは「ITはあくまでもビジネスのための道具」だと見なされがちですが、今日のITにはそれ以上の価値があることを経営にきちんと理解してもらう必要があります。そのためにはIT部門が日頃から、案件の報告以外の場面でも経営と積極的にコミュニケーションを取るよう心掛けるべきでしょう。
── 伝統的な企業に変革をもたらすために欠かせないものは?
野村泰一:部門横断のプロジェクトを立ち上げて、多様性のあるチームでビジネス課題を解決することは、とても重要だと思います。部門間のサイロ化解消にもつながりますし、ビジネス課題をさまざまな視点で見ることができるようになります。
また、そのプロジェクトを通じて、「アジャイル的、SaaS的なやり方が本質的な課題解決につながる」と気づいた人たちを巻き込み、束ねて、改革の機運を高めていくことも大事ですね。実際のところ、私たちのチームでは、社内でITを使ったビジネス課題の解決事例を発表する会を開いたり、識者を招いて勉強会を開催したり、古民家で合宿したりと、さまざまな情報共有の機会を作ることで、「こっちのやり方の方が楽しい」ことを、もっともっと知ってもらおうとしています。同じ仕事をするにしても、「ワクワクする楽しい方」にくる人を増やしたいんです。
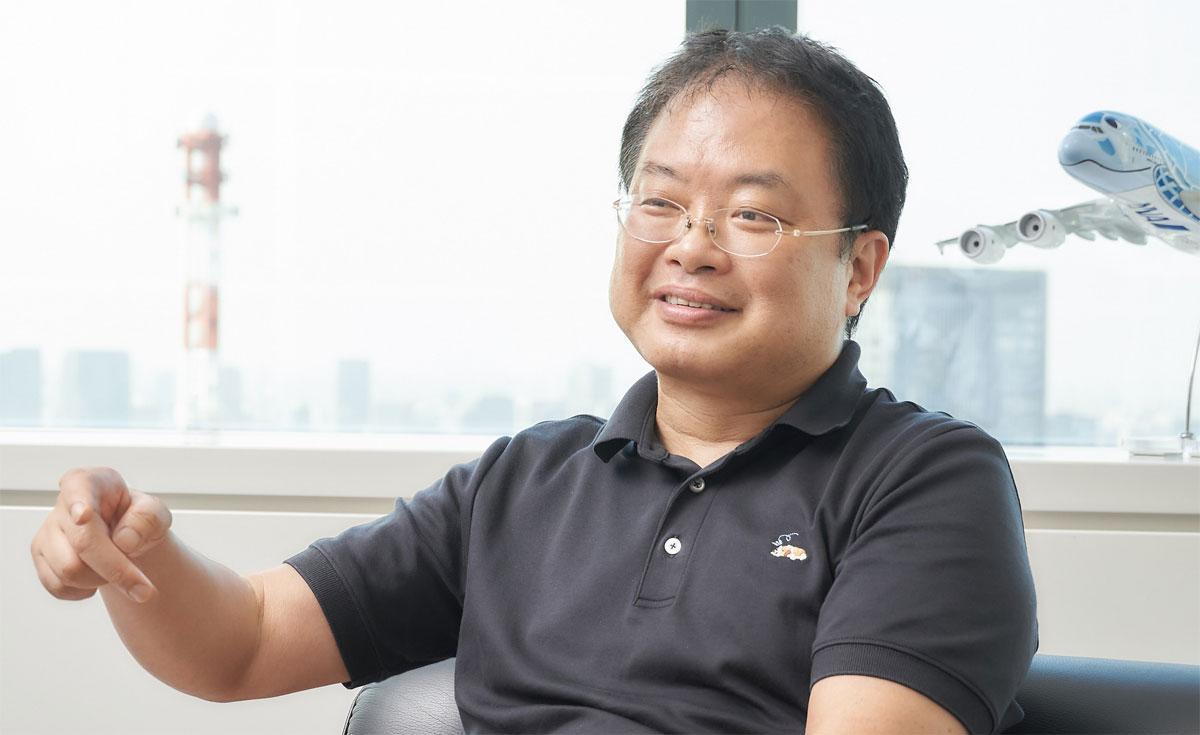
今、私たちが取り組んでいる案件はどれも、とても頭を使うし、新しい技術を勉強しなければならないし、現場とのコミュニケーションも必要だしと、しんどい部分も多いですが、「何のために」「誰のために」という大きな目的がはっきりしているので、「やらされ仕事をするつらさ」や「仕事のための仕事をする徒労感」のようなものとは無縁です。頑張った仕事が人の役に立って感謝され、それによって自信がついて、また新しい課題解決に向かう——そんなサイクルが人を変え、会社にイノベーションを起こす土台になると思うのです。
コロナの影響を受けた航空業界は今、生き残りを賭けた戦いの渦中にいます。そんな今こそ私たちIT部門がハブになり、さまざまな部門の人たちとともにITの力を使って“ANAが再びテイクオフするための取り組み”を進めていきたいと考えています。
【企画・構成・編集:後藤祥子(AnityA)取材:辻村孝嗣・後藤祥子(AnityA) 執筆:吉村哲樹 撮影:永山昌克】
- カテゴリ:
- インタビュー






